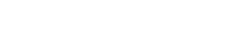「前日の取材ワークショップでは、何を聞けばいいのか正直よくわかりませんでした。『準備』って言われても、実感がなかったんです」
初めて見るパラスポーツの大会。現地に行けば何かが見えてくるかもしれない──そんな思いで、早朝6時すぎ、ホテル前に集合した。
移動の壁、情報の壁。「雨の中、ぐるぐる迷っていました」
観戦当日、最初にぶつかったのは「移動」と「情報」の困難さだった。
「会場は広くて、音声の案内もあまり届かない。地図もピンと来ないし、AirPods Proでチャット通知を読んでやっと把握できるくらい。ディスレクシアの自分には、視覚的な案内がとにかくわかりにくかったです」
山下公園の観戦エリアには段差や傾斜のある芝生が多く、車いすで移動する人たちと一緒のルート探しは一苦労だった。
「みんなで力を合わせて進んだけど、結局、レースが始まっても、選手が見える場所にはたどり着けませんでした」
観戦者のバリアフリー、もっと想像してほしい
選手を間近で見られない──その原因の一つは、沿道に設置された広告の幕だった。
「立ってる人なら見えるけど、車いすの高さからはまったく見えないんです。大会側は、車いすの観戦者の存在をそもそも想定してなかったのでは?」

選手への配慮はされている。でも、「観る側」には届いていない。鴨下さんはそう感じた。
「スタッフのほとんどが健常者で、障害のある観戦者への対応は準備されていないように見えました。自分だったらもっとこうするのに……そう思う場面がいくつもありました」
印象に残ったのは「タンデムバイクの迫力」
そんな中でも、強く印象に残ったのが、視覚障害の選手が後ろに乗る「タンデムバイク」だった。
「あんな大きな自転車、初めて見ました。車いすや義足の選手は知ってたけど、2人で息を合わせて走るって、すごい迫力でした」

一方で、水泳パートは遠くて見えず、「どんな泳ぎをしていたのか想像するしかなかった」という。
「競う姿」より、「支えること」に惹かれた
レースは熱かった。選手も応援する人も、全力だった。でも、鴨下さんは少し違うところに関心が向いていた。

「自分は順位やタイムにあまり興味がないタイプで、プロスポーツ観戦もふだんはしません。だけど、現場で見ているうちに“支える人になりたい”という気持ちが生まれました」
泳ぎが得意な鴨下さんは、「ライフガードやハンドラーのような水辺で支える人」として関わりたいという気持ちになった。
ふわっとした「もやもや」を大切にしたい
「障害って、(自分も含めて)見た目で分からない人も多いし、パラリンピックって、実はごく一部の人のものかもしれない……。そう思うと、ちょっともやっとします。でも、その“もやっと”が、自分にとって大事なんです」
わかりにくいこと、伝えにくいこと、それをそのまま「ある」として言葉にしようとする鴨下さん。その姿は、パラスポーツ取材者として見つめようとする確かなまなざしだった。

「関われる方法は、ひとつじゃない」
誰もが記者やカメラマンになる必要はない。でも、誰かの観戦に付き添う人、応援する人、給水所で水を渡す人、声を届ける人、マップを作ったり、案内する人──パラスポーツ大会に関わる方法は、いくつもある。
鴨下さんの「自分の得意な場所で、誰かを支える」という言葉に、未来のスポーツを楽しむヒントがあった。
(聞き手・編集 佐々木延江)